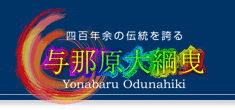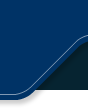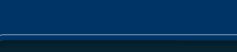|
与那原大綱曳の始まりは、1500年代の尚永王時代までさかのぼるといわれており、現在まで440年余の歴史を誇ります。 |
『与那原町の民話』によると、その昔、害虫が発生し稲が不作で人々は餓死寸前まで追い込まれた年がありました。困り果てた村頭は、姥捨て山に捨てた老人に相談したところ、「野山の草を集めて焼き、皆で鐘やドラを叩き、大声を出しながら綱を曳くように」と教わりました。その結果、害虫はいなくなったとの伝えがあります。 |
|
与那原大綱曳は、他の綱曳とは違う大きな特徴があります。それは、綱の上に支度を乗せることから始まり、綱曳が終了するまでの一連の流れに区切りがなく、すべてが連続した動きであるということです。それぞれの流れを整理すると
特に(5)のカナチ棒が入ってから綱曳が始まるまでは、あっという間の出来事ですが、この流れこそ他の地域にはない与那原大綱曳の醍醐味であり最大の特徴なのです。また、綱を曳く時も単に「引きずる」のではなく、綱本体を上下させながら(地面に叩きつけながら)曳きます。 解説:与那原綱曳資料館館長 上原正己さん |
|
与那原大綱曳は、本番までの間に多くの関連行事があります。祈願祭など、旧暦で決まっている行事もあれば、実行委員会により決定されるものもあります。5月の末頃から8月まで、約3ヶ月間の準備期間を経て本番を迎えます。
|
 |
Copyright 2010 Yonabaru Town Rights Reserved